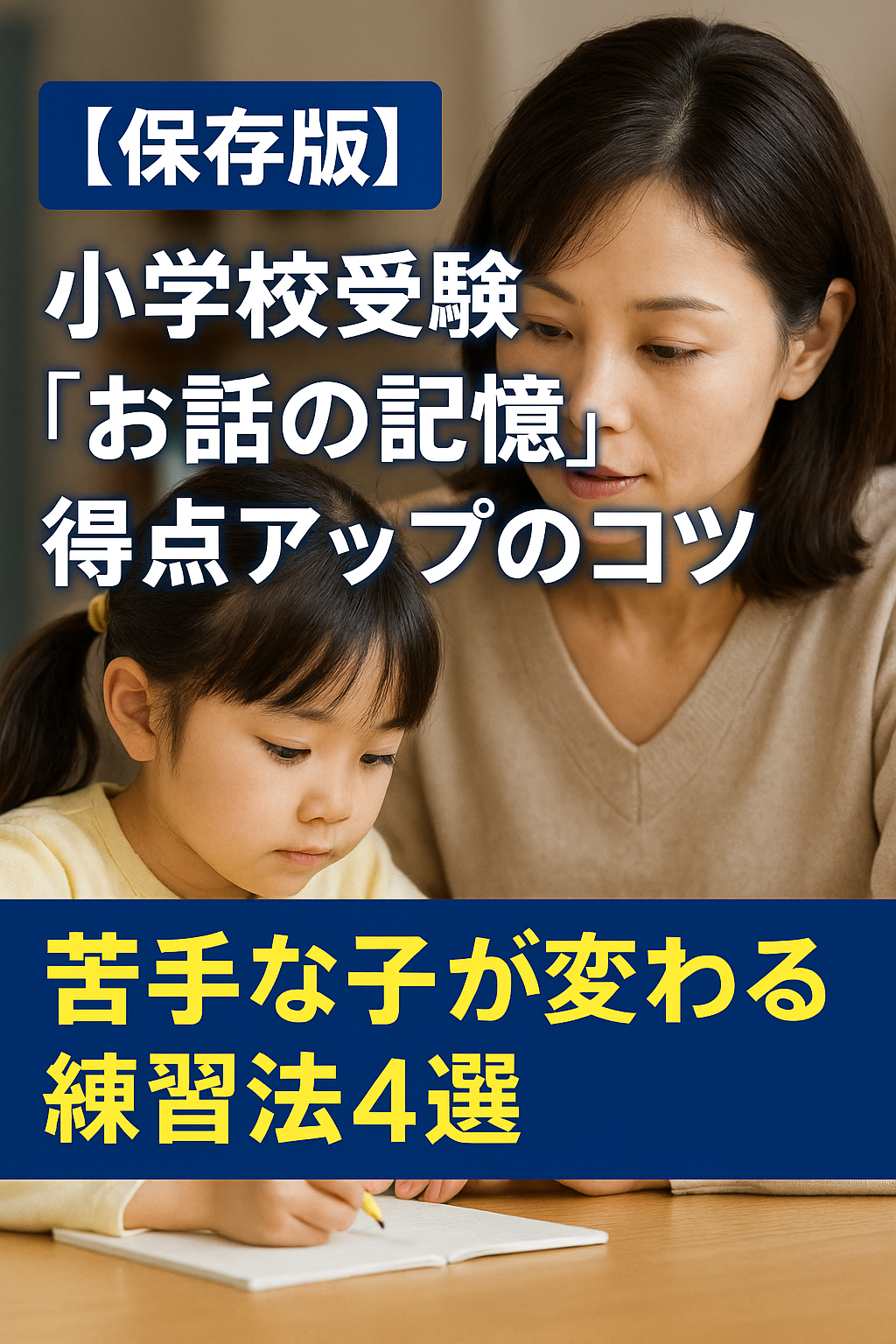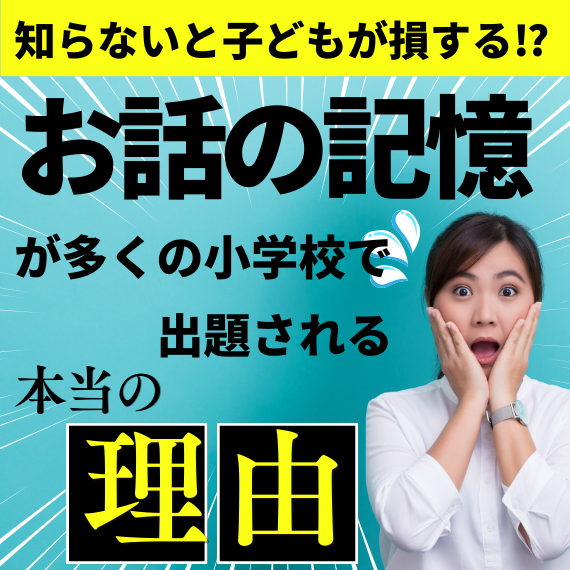目次
小学校受験「お話の記憶」とは?
お話を聞いて、その内容を理解し質問に答える科目が 「お話の記憶」 です。
この課題では、
- 聞く力
- 理解力
- 集中力
- 記憶力
が同時に求められます。
小学校受験「お話の記憶」が苦手…そんなお子さまへ
「最初の方に聞い話をすぐに忘れてしまう」
「長文になると混乱する」
こうした悩みはとても多いですが、実は 正しく練習すれば必ず伸びる科目 です。
この記事では、
今日からできる練習の流れ を丁寧に解説します。
小学校受験「お話の記憶」:出題形式と重視ポイント
お話の記憶は、
「音声で流れてくるお話を聞いて、あとから質問に答える」 形式で出題されます。
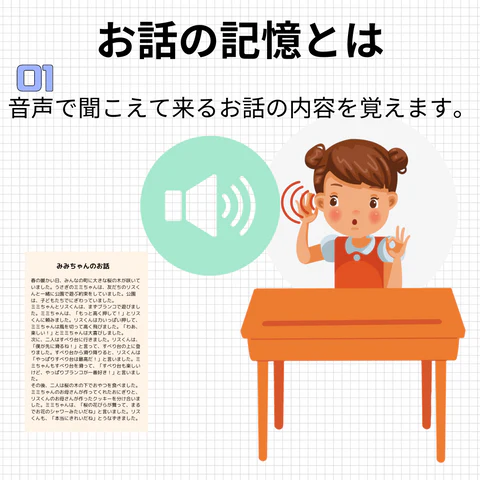
形式は大きく2つ。
① 口頭回答 聞いた内容をそのまま口頭で答える形式。
② 筆記選択式 選択肢の中から正しい答えを選ぶ記述形式。
学校によっては
- 600〜1000字の長文
- 絵選択問題
- 順番並べ替え
など、応用的な出題が増えています。
お話の記憶が見ている本質
- 集中力…最後まで集中して聞ける
- 記憶力…大事な部分を覚えられる
- 理解力…情報を整理して理解できる
これは入学後の 授業を聞く姿勢そのもの と直結しています。
だからこそ、「お話の記憶」は毎年ほぼ必ず出題される重要科目です。
『お話の記憶が苦手』チェックリスト
お話の記憶ができない理由は、大きく3つに分類されます。
まずは、お子さまが どこでつまずいているのか を確認しましょう。
| チェック項目 | できている? |
|---|---|
| お話を最後まで聞くことができない | ☐ 聞き取りの集中が続かない |
| 登場人物や物・数などを聞き逃す | ☐ キーワードを覚えられない |
| 話の順番通りに内容を要約し説明できない | ☐ 記憶を整理するスキルがない |
お話の記憶を得意にするための3つのコツ
1. お話を集中して聞く力を作る
お話の記憶の8割は「聞き方」で決まります。
読む側が少し工夫するだけで、お話を聞く力が変わります。
- テレビや音がない静かな環境で、子どもの目線の高さでお話をする
- 読み手がゆっくり・分かりやすく読む
- 音の強弱・声色を変える・リズミカルに読む・擬音を使う
👉これだけで「お話を最後まで集中して聞けない」が激減します。
2. お話を“イメージ化”して覚える
記憶が定着する子は、聞いた瞬間に 頭の中で絵(映像) にしています。
- 頭の中でお話の場面を想像
- 色や形の特徴から思い出す
👉イメージ化することで、覚えられない・すぐに忘れるを減らせます。
3. 内容を整理・要約する
- 登場人物
- いつ・どこで
- 何をした
👉この“話の流れ・要点”を整理できると、長文でも応用問題にも強くなります。
自宅でできる練習ステップ
STEP1:読み聞かせ
まずは読み聞かせからスタート!子どもがお話に興味を持てるきっかけにしましょう。
STEP2:イメージづくり
- 絵や動画などを見てお話のイメージを作る
- 簡単な絵を描いてみるのも◎
- 人物+物+数を意識
STEP3:短いお話からスタート
苦手な子にいきなり長文は逆効果、短い1文を繰り返す所から。
STEP4:キーワードを強調して読む
聞き逃せないポイントを意識させる。
STEP5:読み聞かせ後に質問する
質問例:「誰が、でてきたかな?」「一番最初にしたことは何?」
この問答が“要約力”を伸ばす基礎になります。
年少〜年長の学習ロードマップ
🥚 年少
聞く力・集中力の土台を作る時期
- 読み聞かせ
- 集中力UP遊び
👉まずこの時期は、お話を聞く・集中力を育てましょう!
🐥 年中
短文〜400字の基礎固め
短いお話からスタート!基礎となる400字程度のお話を覚えましょう
👉この時期にお話を覚える基礎を積み上げます。
🐔 年長
本番レベルの仕上げ
- 600〜1000字の長文
- 絵選択などのひっかけ問題
- 並び替え・要点整理
👉正確さを身に付け本番レベルに仕上げましょう。
3分で“聞く力”がスイッチON!
お話の記憶の前にやるべき集中力UPワーク(無料DL)
お話の記憶が苦手な子多くのは「お話を聞く準備(耳を立てる)」 ができていません。
そこで、年少さんからでもできる
——無料テンプレートを特別公開中!
このトレーニングでは、
- 足ぶみ×リズムで“耳を立てる”
- 触覚×リズムで集中スイッチON
- 親子で楽しくできる記憶体操
お話の記憶の「前準備」として最適です。
📥 まずはこちらから無料DLして、今日から3分で“聞く力”を育ててみてください!
👉3分トレーニング
【教材紹介】家庭で“お話を覚える力”を育てるならこれ!
お話の記憶のコツは分かった。
でも、
- 家でどう教えればいいか分からない
- 正しいステップで練習できているか不安
そこで開発したのが、
⭐ 小学校受験初の特許取得「ピクナイズ練習法」を使った《お話の記憶問題集》
ピクナイズ練習法とは?全体像(4ステップ)
🎨 STEP1:お話を映像化(イメージ化)
する-300x300.png)
イラストで「1シーン」として理解。
🔍 STEP2:重要キーワードを正確に拾う
を「正確に」覚える-300x300.png)
- 視覚強調
- 強調音読
で重要語句(キーワード)を聞き逃さない
🧩 STEP3:要点を整理する(シーン分割)

50〜100字ごとに区切り、
“3語要約”で場面ごとに要点を整理。
🔢 STEP4:お話の順番ミスを防ぐ(色×番号)

赤① → 黄② → 青③ のように視覚的に記憶を補強。
👉 長文でも混乱しにくい理由がここにあります。
家庭での学習に最適な理由
- 年少〜年長まで段階的に伸ばせる
- 親子で楽しく取り組める
- 本番形式で練習できる
- 忘れにくい構造化された学習法
👉 詳細はこちら