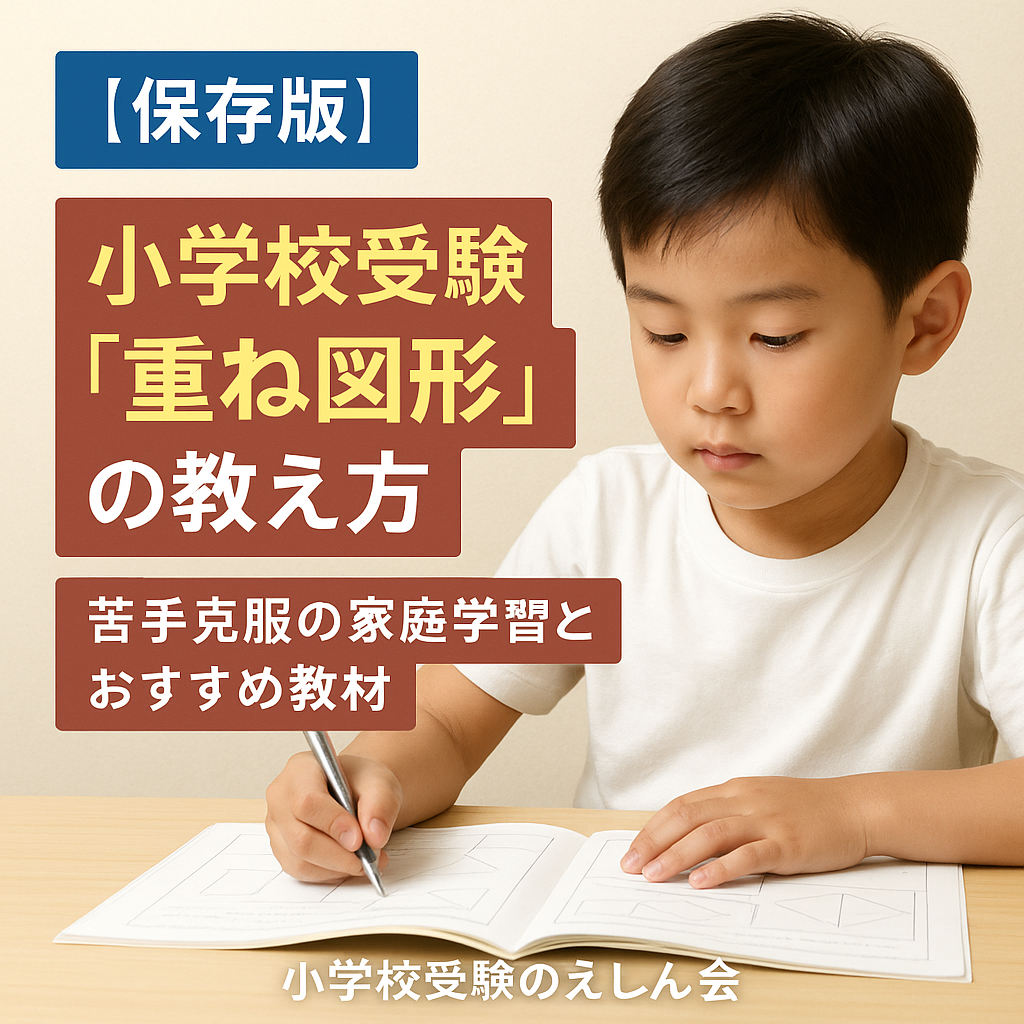目次
小学校受験自宅学習専用教材の絵真会が、重ね図形で伸び悩むご家庭に向けて、今日からできる練習手順とつまずき解消のコツをわかりやすく紹介します。
なぜ重ね図形でつまずくのか
重ね図形は、単純な「見たまま」を答える問題ではありません。
見えない動かした後の図形を頭の中で考える必要があるため、難しくさらに、図形の反転を同時に考える力も求められます。
- 重なりのイメージ変換が必要
- 反転部分を推論する必要
- 全体把握と部分観察の切り替え
合格に必要な3つの力
- 視覚イメージ力:頭の中で「動かす」力
- 反転:/動かす時の反転や対象を理解する力
この2つを体験→イメージ→作図の順で鍛えると、最短で結果が出ます。
家庭でできる教え方(3ステップ)
ステップ1:まずは「動かす」(体験)
図形を実際に重ねたり、ずらしたりして観察します。
- 声かけ例:「この上にこの形をのせたら、どうみえる?」
- 小ワザ:透明のシートを使うと違いが見えやすい
ステップ2:「言葉にする」(言語化)
動かした結果を必ず口に出して整理。
例:どこ+どうなった の型で。お話してみる
ステップ3:「書いて確かめる」(作図)
プリントでは、動かない線を先に描く/動かした線を後で書き加え重なる形に注文するなどのルールを決めて作図をします。
よくあるつまずき&直し方
① 一部だけ見て全体を見失う
対策:1部だけを見るのではなく「左右→上下」の順に図形の線や形のスタート位置全体を確認。
指でなぞりながら、図形をよく観察します。
② 隠れた=消えた、と思ってしまう
対策:「重ねた事で後ろに隠れているだけで存在はする」ことを確認。
クリアシートで重ねる体験を増やす。
③ 焦って適当に線を書かない
対策:「図形の始まりと終わりの線をしっかりたどり→答えを整える」をルーティン化。正確に図形を見る練習。
5日間ミニ練習プラン(保存版)
| 日 | 内容 | 目標 |
|---|---|---|
| 1 | まずは様々な形を実際に重ねて「見える/隠れる」所探し | 体験を通して重なる概念理解 |
| 2 | 図形をずらす・重なる変化をクリアシートを使って観察 | 位置関係の理解 |
| 3 | 簡単な問題を考え方ノートを使ってルールを理解 | 作図の型を定着 |
| 4 | 複雑な重ね方(反転)に挑戦 | 反転を身につける |
| 5 | 問題演習+自己採点 | 本番フォーマットに最適化 |
体験で身につく!絵真会オリジナル教材
プリントだけでは伝わりにくい重ね図形を、親子で「動かしながら」理解できる設計です。
- 図形シート付き:切って重ねて、見える/隠れるを体験
- 考え方ノート:答えよりも「どう考えるか」のプロセス重視
- 家庭学習に最適:短時間×高密度で、忙しいご家庭でも続く
まずは体験→考える→作図の順で学び、プリント学習に橋渡しするのが合格への近道。
親子で「できた!」が増えると、他科目にも好影響が広がります。
重ね図形のよくある質問(FAQ)
Q1. どの学年から始めるべき?
A. 概念体験(重ねる・透かす)は年小から、作図練習は年中に入ってから進めるのが効果的です。
Q2. 家庭での練習時間の目安は?
A. 1回10〜15分を週3〜5回。ダラダラ長くよりも、短く濃くが定着します。
Q3. 苦手意識が強いときの第一歩は?
A. いきなりプリント学習や過去問をせず、図形シートで楽しく体験→補助線のある簡単プリント、の順にしてみましょう。