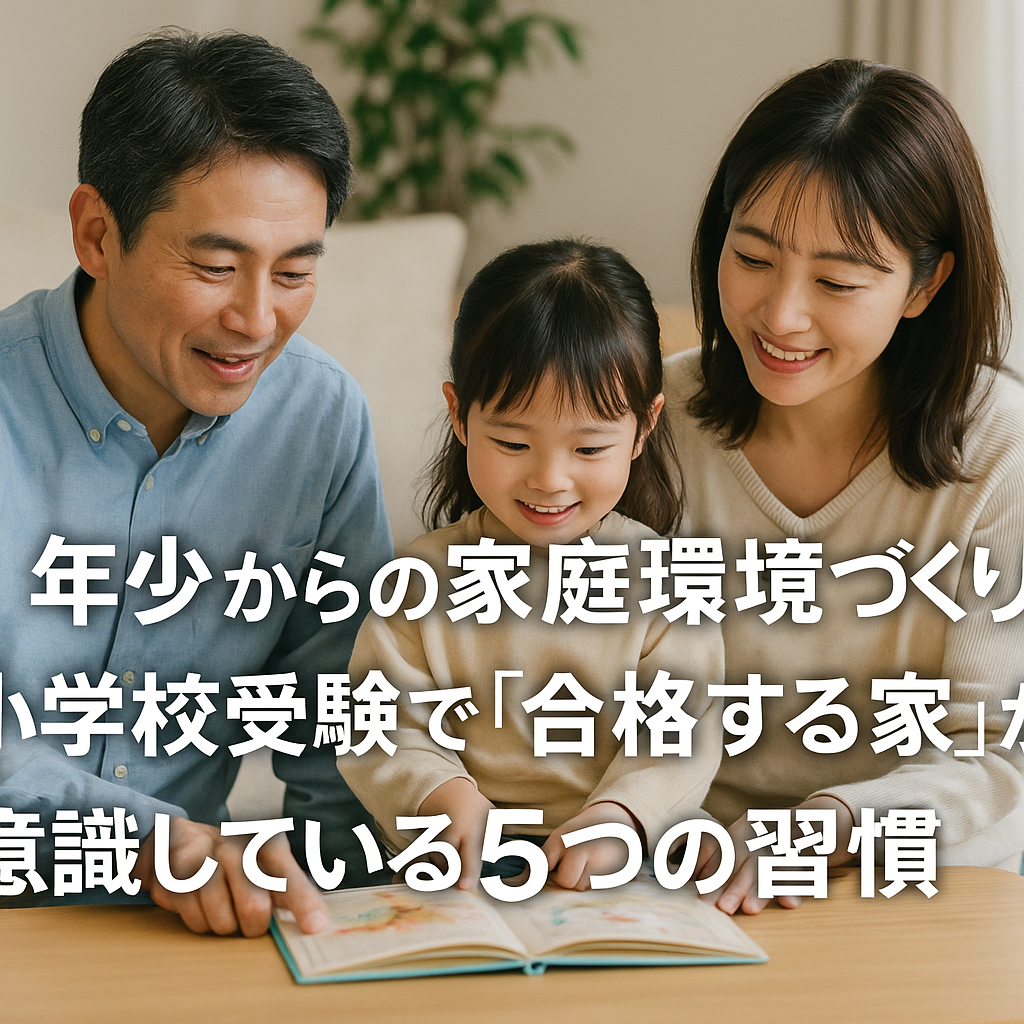目次
年少からの家庭環境づくり|小学校受験で「合格する家」が意識している5つの習慣
「うちの子、まだ年少なのに小学校受験ってもう意識したほうがいいの?」
「プリントをやらせるのはまだ早い気もするし…でも、何もしないのも不安…」
そんなふうに「年少 小学校受験」と検索して、このブログにたどり着いた方も多いと思います。
結論から言うと、年少期の小学校受験準備の中心は、プリントよりも「家庭環境づくり」です。
そして、その「家庭環境づくり」が上手な家ほど、年長になってからの伸び方が全く違います。
なぜ年少から「家庭環境づくり」がそんなに大事なの?
小学校受験の問題を見ると、どうしても
- 図形が難しい
- お話の記憶ができない
- 行動観察が不安
など、「目に見える問題」に意識が向きがちです。
しかし実は、それらの土台になっているのはすべて年少期の生活習慣・家庭の雰囲気・親子の関わり方です。
たとえば、
- 先生の話を最後まで聞く → 日頃の聞く態度
- 落ち着いて座る → 家の中でのルールや生活リズム
- 言葉で気持ちを伝える → 普段の会話量・語彙力
これらはドリルで一気に身に付くものではありません。毎日の積み重ねで育つ力です。
年少からの家庭環境づくり|合格する家が意識している5つの習慣
① 朝・食事・寝る時間が「決まっている」暮らし
合格するご家庭に共通するのは、生活リズムが安定していること。
- 朝は一定の時間に起きる
- 食事時間が大きくズレない
- 寝る時間が遅くなりすぎない
これだけで、集中力・感情の安定・「やるべき時にやる力」が育ちます。
声かけ例:「短い針が8になったら、おやすみの時間だよ」
② 「姿勢」と「聞く態度」を“生活の中で”育てる
年少さんに「ちゃんと座って!」と言っても難しいもの。大切なのは、生活の中で自然に練習すること。
- 食事のとき:椅子に深く座る
- 絵本タイム:読み聞かせの間は静かに座る
声かけ例:「絵本が終わるまで、この椅子で座っていられるかな?」
③ 「会話の質」で語彙力と“考える力”を育てる
年少のうちは、親子の会話が多い家庭は国語力、表現力が成長します。
- 「どうして?」
- 「どっちが好き?」
- 「もし○○だったらどうする?」
これだけで、語彙力・表現力・思考力が伸びます。
会話例:「今日は公園で何が一番楽しかった?」
④ 絵本と本が「手に取りやすい」環境をつくる
年少の主要教材は、実は絵本です。
- 子どもの手が届く本棚
- リビングに数冊の“今読む本”
- 寝る前の読み聞かせを習慣化
これで、語彙・集中力・想像力がぐっと伸びます。
⑤ 外の世界に連れて行き、「好奇心のタネ」をまく
年少期は「見たもの・触れたもの・聞いたもの」すべてが学び。
- 公園で季節の変化を探す
- 図書館・動物園・博物館へ行く
この体験が、行動観察・面接・生活問題の“ネタの宝庫”になります。
声かけ例:「おうちに帰ったら、一番楽しかったことを絵に描こうか」
年少で「やりすぎない」ほうがいいこと
- 難しいペーパーや大量のプリント
- 長時間の机学習
- 年中、長向け教材の先取り
- 他の子と比べて焦る
こうした過剰な先取りは逆に伸びを止めます。
では年少の自宅学習はどこまで?
① 生活習慣・家庭環境づくり(この記事の5つ)
② 遊びながら“考える力”を育てるやさしい教材を少しだけ
たとえば、
- 行動観察・指示行動の基礎遊び
- 短いお話を聞く→答える練習
- パズル・簡単な図形遊び
えしん会では、
- お話が聞けない子のための「お話の記憶スタートセット」
- 行動観察の土台づくりができる基礎教材
など、年少〜年中の遊びを取り入れた“土台づくり”に特化した教材を用意しています。
まとめ|年少は「差をつける」時期ではなく「土台をつくる」時期
年少期は、
- 生活リズムを安定させ
- 姿勢・聞く態度
- 語彙・会話力
- 好奇心のタネ
この4つを整えるだけで、年長での伸び方が大きく変わります。
今日の5つの中から、できそうなものをひとつだけで良いので取り入れてみてください。
“がんばりすぎず、でも確実に”受験の準備を進めていきましょう。